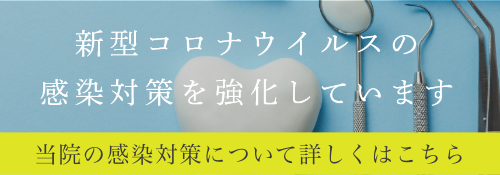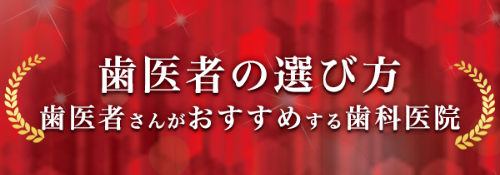1. その口臭、実は歯周病かもしれません

朝起きたときの強い臭いの原因とは
目覚めた直後、「なんだか口が臭う」と感じることはありませんか?これは誰にでも起こる現象ですが、歯周病の兆候である可能性もあります。睡眠中は唾液の分泌量が大幅に減少し、細菌が繁殖しやすくなるため、口腔内では臭いの元となるガスが発生します。特に歯周病が進行している方では、歯周ポケット内の細菌活動が活発になり、揮発性硫黄化合物という悪臭成分が発生します。この臭いは単なる「寝起きの口臭」ではなく、病的口臭の一種です。歯磨きをしても数時間後にまた臭ってくる場合は、セルフケアでは改善できない深い部分に問題が潜んでいる可能性があります。
マスクの中で気づく自分の口臭
マスク生活が続く中、「自分の口臭が気になるようになった」と感じる方が急増しています。これまでは他人に指摘されることで気づくことが多かった口臭も、マスクにこもった息によって、本人が自覚しやすくなりました。実はこの“気づき”は非常に重要なサインです。毎日きちんと歯磨きしているのに臭いが続く場合、考えられる原因は口の奥深く、つまり歯周ポケット内に潜む細菌です。歯周病菌は酸素を嫌い、空気の届かない歯ぐきの深部で繁殖し、強い臭気を発します。市販のマウスウォッシュやブレスケアでは一時的に緩和されても、根本的な解決には至りません。マスクの中で感じた違和感は、専門的な治療を受けるべきタイミングかもしれません。
虫歯ではないのに臭う場合の見落としがちな疾患
「虫歯はないのに口が臭う」—このようなケースは意外に多く、見落とされやすいのが歯周病です。虫歯のように鋭い痛みが出ないため、症状に気づきにくく、悪化するまで放置されがちです。歯周病は、歯と歯ぐきの間にできる“歯周ポケット”に細菌が溜まり、歯肉に炎症を起こす病気です。このポケットの内部では、悪臭の原因となる腐敗ガスが発生し、それが口臭として現れます。しかも、口の中ではこのガスが長時間とどまりやすく、周囲にも気づかれるほどの臭いになることもあります。「虫歯がないから大丈夫」と安心せず、口臭が続く場合は歯周病の検査を受けることが大切です。症状が軽度なうちに発見できれば、治療期間や費用の負担も最小限に抑えられます。
2. なぜ歯周病で口臭が強くなるのか?

歯周ポケット内で増える嫌気性細菌の仕組み
歯周病による口臭の原因は、目に見えない“歯周ポケット”の中に潜んでいます。歯周ポケットとは、歯と歯ぐきの境目が歯周病によって深くなった溝のこと。このポケットの奥深くは酸素が届きにくく、空気を嫌う「嫌気性細菌」にとって非常に繁殖しやすい環境です。こうした細菌は歯ぐきの内側で活動しながら、炎症を引き起こし、膿や腐敗臭を伴うガスを発生させます。特にミュータンス菌やポルフィロモナス・ジンジバリスといった歯周病菌は、揮発性硫黄化合物(VSC)を生成することで知られています。これらの細菌は、毎日のブラッシングでは取り除くことが難しく、歯科での専門的な除去が必要です。つまり、歯周病の臭いは細菌の種類と活動環境によって強くなっていくのです。
硫化水素やメチルメルカプタンなど臭気成分の発生源
歯周病による口臭の正体は、腐敗したような臭いの原因物質「揮発性硫黄化合物(VSC)」です。このVSCは主に3種類あり、中でも臭気が強いのが硫化水素とメチルメルカプタンです。硫化水素は「腐った卵」のような臭い、メチルメルカプタンは「腐敗した野菜」のような臭いが特徴で、どちらもたんぱく質が分解される際に発生します。歯周病が進行すると、歯周ポケット内に炎症が起き、出血や膿が混ざることでタンパク質が豊富な状態になり、これらの成分が大量に生成されやすくなります。つまり、歯ぐきの炎症が強ければ強いほど、より臭いが強くなるメカニズムがあるのです。一般的な口臭ケア用品ではこの化学成分を完全に除去することは難しく、歯科での根本的な治療が求められます。
歯石や舌苔と関係する“口内の汚れ溜まり”
口臭の原因は歯ぐきの奥だけではありません。歯石や舌苔(ぜったい)も、臭いを悪化させる大きな要因です。歯石とは、歯垢が硬くなったもので、表面がざらついているため細菌が付着しやすくなります。この歯石の中で歯周病菌が繁殖し、悪臭のもととなるガスを出すのです。さらに、舌の表面に付着する白や黄ばみのある舌苔も問題です。舌苔には食べかすや古い細胞、細菌などが溜まりやすく、特にメチルメルカプタンの発生源になりやすいとされています。加えて、唾液の分泌が減少していると汚れが洗い流されにくくなり、臭いがこもりやすくなります。歯周病がある方は、歯石や舌苔の管理も含めた総合的なクリーニングを行うことで、臭いの改善効果が高まります。
3. 歯磨きだけでは取れない「隠れた汚れ」
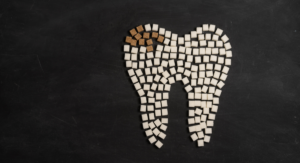
自宅のケアでは届かない歯周ポケットの深部
毎日欠かさず歯磨きをしているのに口臭が改善しない——その原因のひとつが「歯周ポケットの深部」にある汚れです。歯周ポケットは歯と歯ぐきの境目にできる溝で、歯周病が進行するほど深くなり、通常の歯ブラシでは届かなくなります。ここにはプラーク(歯垢)や細菌が蓄積しやすく、やがて悪臭のもととなる揮発性硫黄化合物を発生させます。特に嫌気性菌と呼ばれる細菌は空気を嫌い、酸素の届かない歯周ポケット内で繁殖します。セルフケアで除去できないこれらの細菌は、専門的な器具を用いた歯科でのクリーニングによって初めて取り除くことが可能です。「磨いているのに臭う」という方は、見えない“奥の汚れ”を疑う必要があります。
歯石が放置されると臭いが悪化する理由
歯垢(プラーク)が放置されると、やがて唾液中のミネラルと結びついて石のように硬くなり、「歯石」へと変化します。この歯石の表面はざらざらしており、細菌が定着しやすいため、口の中が常に“細菌の温床”になってしまいます。歯石は一度つくと通常の歯ブラシでは除去できません。そのまま放置すると歯ぐきの炎症が進み、歯周病の悪化とともに臭いも強くなります。特に歯の裏側や歯と歯の間にこびりついた歯石は、臭いの原因物質である揮発性硫黄化合物を発生させる嫌気性菌の住処となります。口臭対策において、歯石の除去は根本的な改善策の一つであり、定期的に歯科医院でプロの手によるクリーニングを受けることが重要です。
舌苔・唾液・補綴物も影響する複合臭とは
口臭の原因は歯ぐきや歯石だけではありません。舌の表面に付着する「舌苔(ぜったい)」や、唾液の量・質、さらには詰め物や被せ物などの補綴物の状態も、臭いに大きく関与しています。舌苔は、食べかすや口腔粘膜の剥がれ、細菌などが付着して形成される白や黄ばみのある汚れです。特に歯周病がある場合は、口腔内の細菌環境が悪化しやすく、舌苔も厚くなり、より強い臭気を放つようになります。また、唾液の分泌が少ないと自浄作用が低下し、汚れが滞留しやすくなります。さらに、古い詰め物や不適合な被せ物の隙間に食物残渣が溜まると、そこからも臭いが発生します。これらの要素が重なることで“複合臭”が生じ、本人が気づかぬうちに慢性的な口臭となって現れるのです。
4. 歯周病の進行とともに悪化する口臭

初期にはほとんど症状がない“沈黙の病気”
歯周病は「サイレントディジーズ(沈黙の病気)」とも呼ばれるほど、自覚症状に乏しい疾患です。初期の段階では、歯ぐきの軽い腫れや出血程度で、痛みを感じることはほとんどありません。そのため、口臭の原因が歯周病だと気づかず、放置されるケースが非常に多く見られます。ところが、歯周病はその静かな進行のなかで、歯周ポケット内に嫌気性菌が増殖し、強烈な臭気を発生させていきます。症状を感じにくいからこそ、本人の意識では「清潔にしているのに臭う」というギャップが生まれ、日常生活に支障をきたすことも。歯周病の初期段階こそ、専門的な診査で早期発見・早期治療を行うことが、臭いの元を断つために最も重要です。
歯ぐきの炎症が悪化すると臭いも強くなる
歯周病が進行すると、歯ぐきの炎症が拡大し、赤く腫れたり出血したりする状態になります。炎症が続くと歯ぐきからの出血だけでなく、膿が出てくることもあり、その膿の中に含まれるタンパク質が分解されることで、強い腐敗臭が生じます。この臭いは単なる口の不快感を超えて、周囲の人にも気づかれるほどの悪臭となることがあります。特に、膿が慢性的に出ている状態では、口臭が常に持続し、本人の自信喪失や対人関係に影響を与えることも少なくありません。炎症が強まるほど、細菌の活動が活発になり、揮発性硫黄化合物(VSC)の濃度も上昇するため、歯周病の進行と口臭の悪化は密接に関連しています。
重度化すると口臭だけでなく歯のグラつきにも
歯周病がさらに重度になると、炎症が歯を支える骨(歯槽骨)にまで及びます。歯槽骨が破壊されると歯がぐらつき始め、最終的には歯が抜けてしまうこともあります。この段階では口臭も極めて強く、腐敗臭や血の混じったような臭いが慢性的に発生するようになります。さらに、歯の隙間が広がることで食べ物が詰まりやすくなり、詰まった食べかすがさらに臭いの原因となります。こうした悪循環により、歯周病が進行すればするほど、口臭はより深刻な状態へと陥ります。しかもこの段階では、歯磨きや市販の口臭対策では全く効果がなく、歯科医による専門的な治療が必要です。見た目の問題や機能的な問題とともに、強い口臭は精神的な負担にもなり得るため、早期の対応が求められます。
5. 歯周病の口臭は「治療」でしか改善できない

歯石除去(スケーリング)で細菌の温床を除去
口臭の主な原因である歯周病菌は、歯の表面にこびりついた「歯石」を住処にしています。歯石は歯垢(プラーク)が唾液中のミネラルと結合して石のように硬化したもので、一度つくと歯ブラシでは落とせません。特に歯と歯ぐきの境目に溜まった歯石は、細菌が長期間潜むことで慢性的な炎症と強い臭いを引き起こします。スケーリングとは、この歯石を専用の器具(スケーラー)を用いて物理的に取り除く処置であり、歯周病治療の第一段階として非常に重要です。歯石を除去することで、細菌の繁殖環境を根本から断ち切り、口臭の大元となる原因を取り除くことが可能になります。セルフケアでは届かない汚れへの唯一の対処法が、歯科でのスケーリングなのです。
歯周ポケットの深部清掃と細菌除去(SRP)
歯石除去だけでは対応できない、歯周ポケットの奥深くに溜まった細菌や汚れには、「ルートプレーニング」と呼ばれるさらに踏み込んだ処置が必要です。これは「スケーリング・ルートプレーニング(SRP)」として行われ、歯の根の表面を滑らかに整え、細菌の再付着を防ぐ目的もあります。SRPは麻酔を使用する場合もありますが、痛みは最小限に抑えられており、進行した歯周病においては非常に効果的な治療法です。特に揮発性硫黄化合物(VSC)を発生させる嫌気性菌が棲みつくのは、まさにこの深い部分です。表面的な清掃では対応できないため、専門的な処置が必要不可欠となります。SRPは、口臭の根本改善に向けた“転換点”といえる治療です。
専門的な歯科検査による原因菌の特定と対策
歯周病の治療は“原因を突き止める”ことから始まります。現在では、歯周病菌の種類や量を検出するための唾液検査やDNA検査が用いられることもあり、患者ごとの菌種に合わせた対策が可能になってきました。特に、ポルフィロモナス・ジンジバリスやタンネレラ・フォーサイシアといったVSCを大量に発生させる菌が確認された場合、除菌効果のある薬剤や、定期的なメンテナンスプログラムの導入が必要になります。こうした専門的な検査は、目に見えない臭いの“見える化”を可能にし、患者自身の理解とモチベーションを高める役割も担っています。原因菌を把握することが、再発予防と長期的な口臭改善に直結するのです。
6. 歯科医院で受けられる口臭対策のステップ

口臭の測定と唾液検査による現状把握
口臭は目に見えない悩みだからこそ、まず「見える化」することが第一歩です。歯科医院では、口臭の強さを数値で測定できる「口臭測定器」や、口腔内の細菌バランスを分析する「唾液検査」を導入しているところもあります。これらの検査によって、臭いの成分(主に硫化水素・メチルメルカプタンなど)や唾液の質・量が明確に把握できるため、原因の特定が容易になります。特に唾液の分泌量が少ない場合は、唾液腺マッサージや水分補給の指導など、根本からの対応が可能になります。口臭に対する不安やコンプレックスは、感覚だけで悩み続けるのではなく、数値とデータで理解することで、より合理的かつ前向きな治療へとつながります。
除菌後の再発予防と正しいブラッシング指導
歯科で歯石を除去し、歯周ポケット内のクリーニングを行った後も、口臭を完全に防ぐには「再発予防」が欠かせません。そこで重要になるのが、患者自身による毎日のセルフケアです。多くの人は正しい歯磨きができているつもりでも、磨き残しや力の入れすぎ、歯間や舌の清掃不足など、自己流ケアには限界があります。歯科医院では、歯の形や歯並びに合わせたブラッシング方法、歯間ブラシやフロス、舌ブラシの使い方を個別に指導することが可能です。また、口臭の原因になりやすい部分(特に奥歯の歯周ポケットや舌苔)を意識してケアすることで、日々の予防効果が高まります。治療後のケアは、専門家のサポートとセットで行うのが、口臭対策の成功の鍵です。
生活習慣(食事・喫煙・ストレス)への歯科的アドバイス
口臭の原因は口腔内だけでなく、日々の生活習慣にも深く関係しています。例えば、ニンニクやネギなどの強い臭いの食事、喫煙、飲酒、さらにはストレスによる唾液分泌の低下などが挙げられます。歯科医院では、こうした生活習慣に対しても専門的な視点からアドバイスが可能です。喫煙は歯ぐきの血流を悪化させ、歯周病の進行を早めるうえ、タールが臭いを吸着しやすくするため、重度の口臭の温床となります。また、ストレスによって唾液の分泌量が減少すると、自浄作用が低下して細菌が繁殖しやすくなるため、口臭が強まる傾向にあります。歯科医院では単なる治療だけでなく、ライフスタイル改善の提案も含めて、トータルに口臭予防を支援しています。
7. 口臭に悩む人がやりがちなNG行動

口臭スプレーやガムでごまかすだけの対処
「とりあえず臭いをごまかしたい」という気持ちから、口臭スプレーやミントガムなどを頻繁に使用する方は少なくありません。これらの製品は、瞬間的に口の中をさわやかに感じさせてくれますが、あくまで“対症療法”であり、根本的な改善にはつながりません。特に、歯周病が原因となっている場合、原因菌は歯周ポケット内や歯石の中に潜んでいるため、いくら表面を香りで覆っても、時間が経てばすぐに悪臭が戻ってきます。こうした対処を続けてしまうと、口臭の本当の原因に気づくタイミングを逃し、病気が静かに進行してしまう恐れがあります。「臭いを隠す」よりも「原因を治す」ことに意識を向けることが、改善への第一歩です。
独自の自己判断による強すぎる口腔ケア
口臭が気になるあまり、「とにかく強く磨けば良い」と考えて、力任せに歯を磨く人もいます。しかしこれは、かえって逆効果です。歯ブラシの圧が強すぎると、歯ぐきが傷ついて炎症を引き起こしたり、歯の表面のエナメル質が削れて知覚過敏を招く可能性があります。また、舌ブラシをゴシゴシとこすりすぎると、舌の表面が傷ついて細菌が入り込みやすくなり、口臭が悪化することもあります。自己流のケアでは、口臭の原因をむしろ強めてしまうリスクがあるのです。歯科医院で正しいブラッシング法や清掃器具の使い方を指導してもらうことで、効率的に臭いの原因を除去し、健康的な口腔環境を保つことができます。
受診を遅らせることによる病状悪化と社会的ストレス
「口臭があるのを知られるのが恥ずかしい」「歯医者で何か言われるのが怖い」と感じて、歯科受診をためらう方も多くいます。しかしその“ためらい”が、結果的に口臭や歯周病の悪化につながってしまうのです。歯周病は放置すればするほど進行し、口臭も強くなっていきます。さらに、口臭が慢性化すると、自分自身の会話や対人関係にも消極的になり、職場や家庭でのストレスを抱えるきっかけにもなります。歯科医院では、専門的な知識をもとに客観的かつ丁寧に診断・対応を行っており、決して恥ずかしがる必要はありません。少しの勇気が、あなたの生活と口腔環境を大きく改善するきっかけになります。相談だけでも構いませんので、まずは受診という一歩を踏み出してみましょう。
8. 歯周病と全身疾患の関係が口臭を長引かせることも

糖尿病との相互関係と口臭の悪化リスク
歯周病と糖尿病は、互いに影響し合う“相互関係”にあることが知られています。血糖値が高い状態では、体の免疫機能が低下し、歯周病菌に対する抵抗力が落ちるため、歯周組織の炎症が悪化しやすくなります。これにより歯周ポケットが深くなり、口臭の原因である揮発性硫黄化合物(VSC)の産生も増加するのです。一方、重度の歯周病は、炎症性サイトカインを通じて血糖コントロールを乱すことがあるため、糖尿病の悪化要因にもなります。このように、口臭という一見“口の中だけ”の悩みが、実は全身の健康と深く関係していることを認識することが重要です。糖尿病の方ほど、定期的な歯科管理が口臭予防にも直結するといえます。
胃腸や副鼻腔などの関連疾患の見落としに注意
口臭の原因が常に歯周病だけとは限らず、他の疾患が隠れていることもあります。特に、慢性胃炎や逆流性食道炎、消化不良による“内臓性口臭”は、独特の酸っぱい臭いや腐敗臭を伴うことがあります。また、副鼻腔炎(蓄膿症)は、鼻と口がつながっている構造上、膿がのどを通って口臭の原因になるケースもあります。これらの疾患は、歯科だけでは診断・治療が難しい場合もあるため、症状が改善しない場合は内科・耳鼻科との連携が必要になることも。歯科医院では、口腔内を詳細に診断したうえで、他科受診の必要性があると判断されれば適切な紹介が行われるため、早めの相談が大切です。自己判断で放置せず、医療機関の連携を活用することで、口臭の原因を見逃さずに済みます。
全身の健康状態を踏まえた口腔ケアの必要性
現代の歯科医療では、「お口の中は健康の入り口」と考え、全身状態と口腔の関係を重視する方向へ進んでいます。高血圧、心疾患、腎疾患など、さまざまな持病を抱える患者においては、歯周病が重症化しやすく、結果として慢性的な口臭が生じる可能性が高まります。さらに、薬の副作用によって唾液の分泌量が減少する「ドライマウス」も、口臭の一因になります。こうした背景を正しく把握した上でのケアを行うには、医科歯科連携や全身疾患に理解のある歯科医師の診察が欠かせません。単なる“歯の問題”として捉えるのではなく、体全体の健康バランスを考えた口腔ケアを行うことで、根本的な口臭の改善へとつながります。
9. 再発しないためのセルフケアと通院のバランス

歯科医院での定期的なメンテナンスの意義
歯周病とそれに伴う口臭は、治療後も「再発しやすい病気」として知られています。そのため、初期治療で症状が改善しても、油断せず定期的な歯科受診を継続することが重要です。多くの歯科医院では、3ヶ月〜6ヶ月に一度の「メンテナンス(定期検診)」を推奨しており、歯周ポケットの深さ測定・歯石除去・プラークコントロールなどを定期的にチェックしていきます。これにより、目に見えない歯ぐきの中での再発を早期に発見し、悪化する前に対処できます。また、口臭に対しても、数値的な変化や舌苔・唾液の状態を把握することで、トラブルの兆候を見逃さずに済みます。継続的なメンテナンスは、治療の「ゴール」ではなく、「スタート」と捉えるべきなのです。
フロス・歯間ブラシ・舌ブラシの正しい使い方
日々のセルフケアでは、歯ブラシだけで口腔内の汚れを完全に除去することは困難です。特に、歯と歯の間や歯周ポケットの入口付近、舌の表面には、細菌や食べかすが残りやすく、これが臭いの原因になります。フロスは歯と歯の接触面のプラーク除去に最適であり、歯間ブラシは歯間部の広い隙間に効果的です。舌ブラシは舌苔(ぜったい)を優しくこすり落とすための専用器具で、口臭対策には欠かせません。ただし、これらの清掃器具も、使い方を誤ると歯ぐきを傷つけたり、清掃効果が得られないことがあります。歯科医院では、患者一人ひとりの口腔状態に合わせた使い方を指導してくれるため、定期的なフィードバックを受けながら正しい習慣を身につけることが肝要です。
日々の習慣と口腔内の菌バランスを整える工夫
口臭の原因となる細菌は、生活習慣の中で大きく変化します。睡眠不足やストレス、喫煙、偏った食生活などは、唾液分泌を減少させたり、免疫力を下げたりすることで、菌のバランスを崩してしまいます。また、口呼吸が習慣化している方は、口腔内が乾燥しやすく、細菌が増殖する環境が整ってしまいます。これを防ぐためには、水分補給や鼻呼吸の促進、規則正しい睡眠と食事が欠かせません。さらに、キシリトール配合のガムを噛むことで唾液の分泌を促す工夫や、乳酸菌配合のオーラルケア製品を取り入れることも、菌のバランスを整える手段として注目されています。こうした日常の中での小さな工夫が、歯科治療の効果を長持ちさせ、口臭の再発を防ぐ大きな力となるのです。
10. 気になる口臭は早めの相談から始めましょう

「恥ずかしい」より「正しく治す」選択を
口臭に悩んでいる方の多くは、「恥ずかしくて誰にも相談できない」と感じています。しかし、口臭は自分では気づきにくく、また、誰かに指摘されると精神的ショックも大きいものです。こうした不安から放置してしまうと、原因となる歯周病などの病気が進行し、より深刻な状態を招くことになります。歯科医院では、デリケートな問題に配慮したカウンセリング体制が整っており、患者様が安心して悩みを打ち明けられる環境づくりが進んでいます。口臭は「隠す」のではなく、「正しく治す」べき症状です。悩みを我慢せず、医療の専門家に相談することが、改善への第一歩になります。
自覚がなくてもプロのチェックで気づくことも
実は、口臭のある人の多くは自分の臭いに気づいていません。これは「嗅覚疲労」と呼ばれる状態で、常に同じ臭いを嗅ぎ続けると脳が順応してしまい、臭いを感じにくくなるためです。そのため、「自分は大丈夫」と思っていても、実際には周囲に不快感を与えているケースもあります。歯科医院では、数値化された検査機器や専門的な問診により、本人では気づきにくい口臭の有無や原因を的確に判断できます。口臭の自覚がないからといって放置せず、定期的なチェックを受けることが予防・早期発見につながります。「念のために見てもらう」程度の気軽な気持ちで相談することが、将来的なトラブルの回避にもなります。
初診カウンセリングでできることと安心の流れ
「いきなり治療されるのでは…」「どんなことを聞かれるの?」と不安に感じる方も多い初診カウンセリングですが、実際にはとても丁寧かつ安心して進められるよう配慮されています。まず、問診票などで生活習慣や悩みの程度、既往歴などを詳しく確認し、患者様の背景に合ったアプローチを検討します。必要に応じて、口腔内の視診や口臭測定器によるチェック、唾液検査なども行います。そのうえで、すぐに治療が必要な症状があれば応急処置を行い、長期的な治療や予防が必要な場合は、わかりやすい説明を通して無理のない治療計画を提案します。いきなり治療を進めるのではなく、患者様の理解と同意を大切にする流れなので、「まず相談だけしてみよう」という気持ちでも十分です。
監修:青山一丁目 麻布歯科
所在地〒:東京都港区赤坂8-5-32 田中駒ビル1F
電話番号☎:03-6434-9877
*監修者
青山一丁目 麻布歯科
ドクター 安達 英一
*出身大学
日本大学歯学部
*経歴
・日本大学歯学部付属歯科病院 勤務
・東京都式根島歯科診療所 勤務
・長崎県澤本歯科医院 勤務
・医療法人社団東杏会丸ビル歯科 勤務
・愛育クリニック麻布歯科ユニット 開設
・愛育幼稚園 校医
・愛育養護学校 校医
・青山一丁目麻布歯科 開設
・区立西麻布保育園 園医
*所属
・日本歯科医師会
・東京都歯科医師会
・東京都港区麻布赤坂歯科医師会
・日本歯周病学会
・日本小児歯科学会
・日本歯科審美学会
・日本口腔インプラント学会
投稿日:2025年7月14日