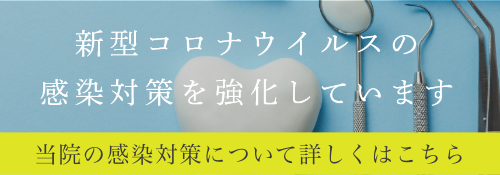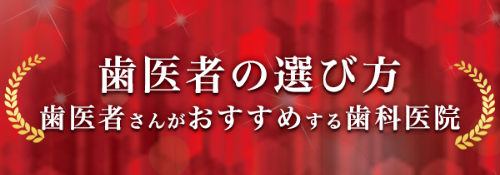「血糖値が下がりにくい…」その原因、お口の中にあるかもしれません

歯周病が治りにくいと感じる理由
「毎日きちんと歯磨きをしているのに、歯ぐきの腫れや出血がなかなか治らない」と感じている場合、その背景に糖尿病が影響している可能性があります。糖尿病をお持ちの方は、そうでない方に比べて歯周病が悪化しやすく、また治りにくい傾向にあることが分かっています。
その主な理由は、高血糖の状態が続くことで、体を細菌から守る白血球の機能が低下し、感染に対する抵抗力が弱まるためです。さらに、高血糖は組織の修復能力を妨げるため、炎症が起きた歯ぐきの治癒を遅らせます。
また、唾液の分泌量が減少し口の中が乾きやすくなる(ドライマウス)ことも、細菌が繁殖しやすい環境をつくり、歯周病のリスクを高める一因となります。
このように、歯周病の悪化は単なるお口のケアの問題だけでなく、糖尿病という全身疾患の状態が深く関わっているのです。
糖尿病と口のトラブルを切り離せない現実
歯周病は、糖尿病と密接な関連がある主要な口腔合併症の一つとして扱われています。これは、糖尿病が歯周病を悪化させるだけでなく、逆に歯周病と糖尿病は相互に影響し合うことが報告されており、血糖コントロールが難しくなる可能性があります。
歯周病は、歯周ポケットで細菌が繁殖し、慢性的な炎症が続く病気です。この炎症によって生み出される炎症性物質(TNF-αなど)が血流に乗って全身を巡ると、血糖値を下げるホルモンであるインスリンの働きを阻害(インスリン抵抗性)してしまいます。
その結果、血糖コントロールがますます難しくなるという悪循環に陥るのです。お口のトラブルは、もはや口だけの問題ではなく、糖尿病という全身疾患の管理と切り離しては考えられない重要な要素と言えます。
自分を責めずに、まず知ってほしいこと
歯周病がなかなか改善しないことで、「自分の歯磨きの仕方が悪いのではないか」とご自身を責めてしまう方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、これまで述べてきたように、糖尿病と歯周病の関係は非常に複雑であり、個人の努力だけでコントロールするのが難しい側面があります。大切なのは、ご自身を責めることではなく、まずこの「歯周病と糖尿病の密接な関係」を正しく知っていただくことです。
そして、この関係は裏を返せば、歯科治療によってお口の炎症をコントロールすることが、血糖値の改善に良い影響を与える可能性がある、という希望にも繋がります。お口の健康管理は、糖尿病治療の重要な一環です。まずは専門家である私たちに相談し、ご自身の体の状態を正しく理解することから、この悪循環を断ち切る一歩を始めてみませんか。
「歯周病」と「糖尿病」──それぞれの病気を正しく理解する

歯周病は「感染」と「炎症」が鍵となる病気
歯周病は、お口の中に存在する細菌による「感染症」です。歯磨きで落としきれなかったプラーク(歯垢)の中に潜む歯周病菌が、歯と歯ぐきの境目(歯周ポケット)で増殖し、毒素を出すことで歯ぐきに「炎症」を引き起こします。これが初期段階の歯肉炎です。
この炎症が続くと、私たちの体を守るはずの免疫反応が過剰になり、歯周病菌だけでなく、歯を支える大切な骨(歯槽骨)まで破壊し始めます。これが歯周炎です。痛みなどの自覚症状がないまま静かに進行するため、気づいた時には歯がグラグラになってしまうことも少なくありません。
つまり歯周病は、単なる口の汚れが原因ではなく、細菌感染によって引き起こされる慢性的な炎症性の病気であるという点が、重要なポイントです。この「炎症」をコントロールすることが、歯周病治療の鍵となります。
糖尿病が全身に与える影響とは
糖尿病は、血液中のブドウ糖の濃度(血糖値)が高くなる状態が続く病気です。食事で摂取した糖をエネルギーとして利用するために不可欠なホルモン「インスリン」の分泌が不足したり、その働きが悪くなったりすることで発症します。血糖値が高い状態が続くと、全身の血管が傷つき、様々な合併症を引き起こす可能性があります。代表的なものに網膜症、腎症、神経障害がありますが、その影響は全身に及ぶため、心筋梗塞や脳梗塞などのリスクも高めます。
このように、糖尿病は血糖値だけの問題ではなく、血管を通じて全身の健康を脅かす「全身疾患」です。日々の食事療法や運動療法、薬物療法によって血糖値を良好な状態にコントロールし、これらの合併症を予防することが治療の重要な重要な目標となります。
この2つが重なると、なぜ悪循環になるのか
歯周病と糖尿病は、それぞれ独立した病気でありながら、互いの症状を悪化させる非常に密接な関係にあります。まず、歯周病によって歯ぐきで起きている慢性的な「炎症」は、血糖値を下げるインスリンの働きを妨げる物質(炎症性サイトカイン)を血液中に放出します。これにより、血糖コントロールが難しくなり、糖尿病が悪化しやすくなります。
一方で、糖尿病で高血糖の状態が続くと、体の免疫機能が低下し、細菌への抵抗力が弱まります。また、組織の修復能力も落ちるため、歯周病にかかりやすく、一度発症すると治りにくくなります。
このように、歯周病が糖尿病を悪化させ、糖尿病が歯周病を悪化させるという「負の連鎖」が生じてしまうのです。この悪循環を断ち切るためには、糖尿病の治療と歯周病の予防・治療を同時に進めることが不可欠です。
歯周病と糖尿病をつなぐ「炎症」のメカニズム

炎症性サイトカインがもたらす血糖コントロールへの影響
歯周病は、歯ぐきに慢性的な炎症が続く病気です。この炎症が起きている組織では、「TNF-α(腫瘍壊死因子アルファ)」をはじめとする様々な「炎症性サイトカイン」と呼ばれる物質が作り出されます。これらの物質は、本来体を守るための免疫反応に関わりますが、歯周病が進行すると過剰に産生され、歯ぐきの血管から血流に乗って全身へと運ばれてしまいます。
そして、全身を巡る中で、血糖値を下げる唯一のホルモンである「インスリン」の働きを鈍らせてしまうのです。これを「インスリン抵抗性」と呼びます。糖尿病の患者様にとって、インスリンが効きにくくなることは、血糖コントロールを著しく困難にさせます。つまり、お口の中の局所的な炎症が、血流を介して全身に影響を及ぼし、糖尿病の管理を難しくする直接的な原因の一つとなるのです。
高血糖状態が歯ぐきの免疫力を低下させる
一方で、糖尿病による高血糖の状態も、歯周病を悪化させる大きな要因となります。血液中の糖分が多い状態が続くと、体を細菌感染から守る白血球(特に好中球)の機能が低下し、お口の中の歯周病菌に対する抵抗力が弱まってしまいます。
また、高血糖は体内のタンパク質と糖が結びつく「糖化」という反応を促進し、「AGEs(終末糖化産物)」という老化物質を蓄積させます。このAGEsは、歯ぐきなどの組織に炎症を引き起こしやすくするだけでなく、組織の修復を妨げる働きも持っています。
その結果、糖尿病の患者様は歯周病にかかりやすく、一度発症すると炎症が広がりやすく治りにくい、という悪循環に陥りやすくなります。血糖コントロールが、お口の免疫力を維持する上でも重要であることが分かります。
口腔内の炎症が「全身疾患」を悪化させる仕組み
お口は体の一部であり、決して独立した器官ではありません。歯周病によってお口の中に生じた慢性的な炎症は、糖尿病だけでなく、他の全身疾患にも影響を及ぼすことが知られています。歯周病菌そのものや、歯ぐきの炎症によって産生された炎症性サイトカインが血流に入ることで、体は常に弱い炎症にさらされた状態(慢性炎症)になります。
この慢性炎症は、血管の内壁を傷つけ、動脈硬化との関連が示唆されており、リスクに影響し得ると考えられています。動脈硬化が進行すると、心筋梗塞や脳梗塞といった命に関わる病気のリスクが高まります。
このように、お口の中の炎症をコントロールすることは、歯を守るだけでなく、血管の健康を守り、ひいては全身疾患の悪化を防ぐための重要な「予防」策となるのです。
「歯周治療で血糖値が下がる?」──医療連携で見えてきた希望

歯周治療が糖尿病管理に好影響を与える研究結果
「歯周病の治療をしたら、血糖値まで改善した」という話を聞いたことがあるかもしれません。これは決して偶然ではなく、多くの臨床研究によって科学的な根拠が示されつつあります。国内外の研究報告によると、歯周病にかかっている糖尿病患者様が、歯石の除去といった基本的な歯周治療を受けることで、血糖コントロールの指標である「HbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)」の値が一部の臨床研究でHbA1cの改善が報告されていますが、効果の程度には個人差や研究間の幅があります。
これは、歯周病治療によってお口の中の慢性的な炎症が抑えられると、インスリンの働きを邪魔していた炎症性物質(サイトカイン)の産生が減少し、インスリン抵抗性が改善するためと考えられています。もちろん、歯周病治療だけで糖尿病が治癒するわけではありません。
しかし、内科での治療に加えて歯科でのアプローチを組み合わせることが、糖尿病という全身疾患の管理に良い影響を与えうる、という希望が見えてきているのです。
歯科と内科の連携で広がる治療の可能性
歯周病と糖尿病が互いに影響し合うという事実は、もはや歯科、あるいは内科という一つの診療科だけで完結する問題ではないことを示しています。そこで重要になるのが、歯科と内科が協力して患者様の治療にあたる「医科歯科連携」という考え方です。
内科医が血糖値を管理し、歯科医がお口の炎症をコントロールする。それぞれの専門家が患者様の状態(血糖値、服用薬、歯周病の進行度など)を共有し、治療計画を連携させることで、より安全で効果的な治療が可能になります。
例えば、血糖コントロールが安定している時期に集中的な歯周治療を行ったり、歯科治療が血糖値に与える良い影響を内科医が評価したりと、相乗効果が期待できます。お口の健康から全身疾患の予防・管理へとつなげるこの連携は、治療の可能性を大きく広げ、患者様がより良い健康状態を維持するための強力なサポートとなります。
治療を受ける前に知っておきたい全身状態の確認項目
糖尿病をお持ちの方が安全に歯科治療を受けるためには、ご自身の全身状態を歯科医師に正確に伝えることが非常に重要です。特に以下の情報は、必ず治療前にお知らせください。まず、最新の血糖コントロール状態です。特に「HbA1c」の値は、歯科治療のリスクを判断する上で重要な指標となります。血糖コントロールが著しく不安定な場合、治療後の感染リスクが高まったり、傷の治りが遅れたりする可能性があるためです。
次に、服用しているお薬の内容です。インスリン注射や血糖降下薬の種類、服用時間などを正確に伝えるため、「お薬手帳」を必ずご持参ください。
また、糖尿病の他の合併症(腎臓病、心臓病、網膜症など)の有無や、かかりつけの内科医の連絡先も大切な情報です。これらの情報を共有していただくことで、私たちは全身状態を十分に考慮した上で、重要な安全で適切な治療計画を立てることができます。
今すぐできる「歯周病・糖尿病」管理の第一歩

歯科受診前に確認しておきたい血糖コントロールの目安
糖尿病をお持ちの方が安全に歯科治療を受ける上で、血糖値が安定していることは非常に重要な条件です。特に抜歯などの出血を伴う治療では、高血糖状態だと感染のリスクが高まったり、傷の治りが遅れたりする可能性があります。
一般的な目安として、過去1〜2ヶ月の血糖値の平均を示す「HbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)」が7.0%未満であることが望ましいとされていますが、これはあくまで一つの目安です。ご自身の状態によって適切な判断は異なりますので、自己判断はせず、まずはかかりつけの内科医に「歯科治療を受ける予定がある」とご相談ください。その上で、歯科医師に最新のHbA1cの値や空腹時血糖値、服用中のお薬(お薬手帳を持参)を正確にお伝えいただくことが、安全な治療への第一歩となります。
また、治療は空腹時やインスリン投与直後を避け、心身ともにリラックスできる午前中の時間帯に予約するなど、低血糖のリスクにも配慮することが大切です。
定期検診で行うべきチェック項目
糖尿病をお持ちの方の歯科定期検診では、一般的な検診内容に加え、特に注意深くチェックすべき項目があります。まず、歯周病の進行度を客観的に評価するため、「歯周ポケットの深さの測定」と「測定時の出血の有無」を全ての歯で確認し、その変化を継続的に記録します。
次に、磨き残したプラーク(歯垢)の付着状態を専用の染め出し液などで確認し、セルフケアが適切に行えているかを評価します。さらに、外からでは見えない歯を支える骨の状態を把握するため、定期的な「レントゲン検査」も欠かせません。
加えて、糖尿病の影響で起こりやすい「口腔乾燥(ドライマウス)」の兆候がないか、舌や粘膜の状態も確認します。これらの専門的なチェックを定期的に行うことで、歯周病のわずかな変化や再発のサインを早期に発見し、重症化する前に対処する「予防」的な管理が可能になります。
毎日のセルフケアで意識したい3つのポイント
歯科医院での専門的なケアと並行して、歯周病と糖尿病を管理する上で重要な基本となるのが、ご自身で行う毎日のセルフケアです。特に意識していただきたいポイントは3つあります。
第一に、「丁寧なブラッシング」です。歯と歯ぐきの境目に歯ブラシの毛先を45度の角度で当て、力を入れすぎず優しく小刻みに動かし、プラークを丁寧に取り除きましょう。
第二に、「歯間清掃の習慣化」です。歯ブラシだけでは取り切れない汚れが残りやすく、フロスや歯間ブラシの併用が推奨されます。歯と歯の間の汚れは、デンタルフロスや歯間ブラシを必ず併用して清掃してください。
第三に、「生活習慣の管理」です。禁煙を心がけ、バランスの良い食事を規則正しく摂ることは、血糖コントロールを安定させ、結果的に歯ぐきの免疫力を高め、歯周病の予防に繋がります。ご自身に合ったケアの方法は、歯科医院で指導を受けることをお勧めします。
「どんな歯医者を選べばいい?」──安心して相談できる医院の見極め方

糖尿病患者への配慮がある歯科医院とは
糖尿病という全身疾患をお持ちの患者様にとって、歯科医院選びは特に慎重に行うべきです。安心して治療を任せられる医院は、初診の問診時から糖尿病について深く関心を示します。具体的には、HbA1cの数値や血糖コントロールの状態、かかりつけの内科医、服用中のお薬(お薬手帳の確認)について詳しく質問し、全身状態を正確に把握しようと努めます。
また、低血糖発作のリスクを避けるため、治療の予約時間を午前中に設定するなどの配慮をしてくれるかどうかも一つの指標です。さらに、歯科医師や歯科衛生士が、歯周病と糖尿病が相互に影響し合う関係性を、患者様の目線に立って分かりやすく説明できるかどうかも重要です。お口の中を単なる一部分としてではなく、全身の健康と繋がる大切な器官として捉え、患者様の背景にある全身疾患を十分に理解した上で治療計画を立ててくれる医院を選びましょう。
医科連携や生活習慣指導を行っているか確認
歯周病と糖尿病の悪循環を断ち切るためには、歯科と内科が連携する「医科歯科連携」が非常に効果的です。信頼できる歯科医院は、患者様のかかりつけ医と積極的に情報交換を行う姿勢を持っています。
例えば、現在の歯周病の状態や治療計画を記した情報提供書を作成し、内科医と共有することで、より安全で質の高い治療に繋がります。内科医は血糖コントロールの観点から、歯科医はお口の炎症コントロールの観点から、それぞれの専門性を活かして一人の患者様をサポートする体制です。
また、歯周病も糖尿病も生活習慣と深く関わる病気であるため、単に歯の治療をするだけでなく、食事や禁煙といった生活習慣の改善について、予防の観点からアドバイスをしてくれる医院も、長期的な健康を考えてくれるパートナーとして心強い存在と言えるでしょう。
カウンセリング重視の医院が信頼できる理由
糖尿病という持病を抱えながら歯科治療を受けることに対し、多くの患者様が不安を感じています。そうした不安に寄り添い、信頼関係を築く上で欠かせないのが、治療前のカウンセリングです。信頼できる医院は、検査結果だけを伝えてすぐに治療を始めるのではなく、まず患者様のお話や悩みをじっくりと聞くための時間を確保します。
そして、現在のお口の状態、歯周病と糖尿病の関係、なぜその治療が必要なのか、治療に伴うリスク、期待できる効果などを、患者様が十分に理解・納得できるまで丁寧に説明します。治療の選択肢が複数ある場合は、それぞれのメリット・デメリットを公平に提示し、患者様自身が主体的に治療法を選べるようサポートします。
このような丁寧な対話を通じて、患者様の不安を和らげ、二人三脚で治療に取り組む姿勢を示してくれる医院を選びましょう。
よくある質問(FAQ)──不安や疑問を一つずつ解消

Q1:血糖値が高くても歯の治療は受けられますか?
血糖コントロールの状態は、歯科治療の安全性に大きく影響します。血糖値が著しく高い状態では、体の免疫機能が低下して感染しやすくなったり、治療後の傷の治りが遅れたりするリスクが高まります。
そのため、抜歯などの外科的な処置については、血糖コントロールが比較的安定している時期に行うのが原則です。一般的な目安として、HbA1cが7.0%未満であることが望ましいとされていますが、これはあくまで指標の一つです。急な痛みなど緊急の対応が必要な場合はもちろん治療を行いますが、計画的な治療に関しては、まずかかりつけの内科医にご相談いただき、現在の全身状態について歯科医師に正確にお伝えいただくことが不可欠です。
自己判断で受診をためらうのではなく、まずは専門家である私たちにご相談ください。内科医と連携を取りながら、安全な治療のタイミングと方法を一緒に考えていきます。
Q2:麻酔や薬の影響はありますか?
糖尿病をお持ちであるからといって、歯科治療で麻酔が使えないわけではありません。通常、治療で用いる局所麻酔は、適量を守れば体への影響は少なく、血糖コントロールが安定していれば安全に使用できます。麻酔薬に含まれる血管収縮薬(アドレナリン)が血糖値をわずかに上昇させる可能性も指摘されますが、治療中の痛みを抑えることで体へのストレスを軽減するメリットの方が大きいと考えられています。
また、治療後に処方される抗生物質や痛み止めについても、糖尿病の状態や服用中のお薬との飲み合わせを十分に考慮して選択します。そのためにも、「お薬手帳」を必ずご持参いただき、服用されている全てのお薬を正確に把握させていただくことが重要です。ご自身の判断でお薬を中断したりせず、不安な点は必ず治療前にご質問ください。
Q3:通院の頻度はどのくらいが理想ですか?
糖尿病をお持ちの方は、歯周病を発症・悪化させるリスクが比較的高いため、一般的な方よりも短い間隔での定期的なメンテナンスが推奨されます。
理想的な通院頻度は、歯周病の進行度や血糖コントロールの状態によって一人ひとり異なりますが、治療が一段落した後の安定した時期でも、1ヶ月から3ヶ月に一度の受診が望ましい場合が多いです。短い間隔で検診を行うことで、歯周病の再発のサインを早期に発見し、重症化する前に対処できます。
また、専門家によるクリーニングで、ご自身の歯磨きでは除去しきれない細菌の膜(バイオフィルム)を定期的に取り除くことは、お口の中の炎症をコントロールし、ひいては血糖値の安定にも繋がるという、予防の観点から非常に重要です。かかりつけ医に通うのと同じように、歯科医院を全身疾患管理のパートナーとしてご活用ください。
「放置しないこと」が重要な予防──日常生活でできる炎症コントロール

食事・睡眠・ストレスが歯周病に与える影響
歯周病や糖尿病は、日々の生活習慣と深く関わっています。例えば、糖質の多い食事は血糖値を上げるだけでなく、歯周病菌の栄養源となり、お口の環境を悪化させます。一方で、ビタミンや食物繊維が豊富なバランスの取れた食事は、歯ぐきの健康を保ち、体の抵抗力を高めます。
また、睡眠不足や精神的なストレスは、体の免疫機能を低下させ、炎症を悪化させる原因となります。ストレスを感じると分泌されるホルモンが、歯ぐきの炎症を促進し、歯周病の進行を早める可能性も指摘されています。
特に糖尿病をお持ちの方は、ただでさえ感染症にかかりやすい状態にあるため、規則正しい生活を送り、心身のバランスを整えることが、お口の中の炎症をコントロールし、ひいては全身の健康を維持するための重要な「予防」策となるのです。
禁煙がもたらす炎症改善の効果
喫煙が歯周病の主なリスク因子の一つであることは、科学的に明確に示されています。タバコに含まれるニコチンは、歯ぐきの血管を収縮させ、血流を悪化させます。これにより、歯ぐきへの酸素や栄養の供給が滞り、組織の修復能力が低下します。
また、体の免疫機能そのものを低下させるため、歯周病菌と戦う力が弱まり、炎症が悪化しやすくなります。さらに、喫煙は歯周病の初期症状である「歯ぐきからの出血」を抑えてしまうため、病気の発見が遅れる原因にもなります。禁煙をすることで、これらの悪影響は改善に向かいます。
歯ぐきの血流が回復し、免疫機能が正常化することで、炎症が治まりやすくなり、歯周病治療の効果も格段に高まります。禁煙は、糖尿病の合併症予防にとっても極めて重要であり、お口と全身の健康を守るための、非常に価値のある選択です。
糖尿病管理と口腔ケアを両立させる生活習慣
糖尿病の管理とお口のケアは、決して別々の事柄ではありません。むしろ、両者は密接に連携しており、日々の生活の中で一体として捉えることが大切です。例えば、血糖コントロールに配慮したバランスの良い食事は、そのまま歯周病の予防にも繋がります。食後の歯磨きを、血糖値のチェックや服薬と同じように日々のルーティンに組み込むことで、習慣化しやすくなるでしょう。
また、糖尿病の方は唾液の分泌が減少し、お口が乾きやすくなる傾向があります。こまめな水分補給を心がけることは、ドライマウスの予防だけでなく、お口の中の細菌を洗い流す助けにもなります。
このように、糖尿病管理の一環としてお口のケアを位置づけ、内科医と歯科医の両方と定期的にコミュニケーションを取ることが、歯周病と糖尿病の悪循環を断ち切り、全身の健康を維持するための鍵となります。
歯周病と糖尿病を同時にケアする意味──未来の自分を守る選択

治療の「目的」は症状の改善だけではない
糖尿病をお持ちの方にとって、歯周病治療の目的は、単に歯ぐきからの出血を止めたり、腫れを引かせたりすることだけに留まりません。その本質的な目的は、お口の中から慢性的な「炎症」を取り除き、体全体の炎症の総量を減らすことにあります。歯周病による炎症は、血糖値を下げるインスリンの働きを妨げ、血糖コントロールを難しくする一因となります。
したがって、歯科治療によってお口の炎症をコントロールすることは、症状の改善はもちろんのこと、血糖管理をサポートし、歯周病と糖尿病の悪循環を断ち切るための積極的な一手となります。これは、将来起こりうる糖尿病の合併症に対する重要な「予防」策であり、未来のご自身の健康を守るための治療なのです。
口腔の健康が全身疾患のリスクを下げる理由
お口は、全身の健康状態を映す鏡であり、また全身に影響を及ぼす入り口でもあります。歯周病によって歯ぐきに慢性的な炎症があると、そこから炎症を引き起こす物質(炎症性サイトカイン)や歯周病菌が血流に乗って全身を巡ります。これらの物質は、血管の内壁にダメージを与えて動脈硬化を促進し、心筋梗塞や脳梗塞といった、糖尿病の重大な合併症である血管系の疾患のリスクを高めることが分かっています。
つまり、お口の健康を守り、歯周病による炎症をコントロールすることは、歯を失うのを防ぐだけでなく、血管の健康を守り、ひいては命に関わる「全身疾患」の発症リスクを低減させることに直結します。口腔ケアは、全身の健康を守るための基本的な「予防」医療の一つと言えるのです。
医療チームと二人三脚で進める健康管理
歯周病と糖尿病という、互いに深く関連する病気を管理していく上で、患者様は決して一人ではありません。あなたの健康は、糖尿病を診る内科医と、歯周病を診る歯科医という医療チームが連携してサポートします。この「医科歯科連携」を成功させる鍵は、患者様ご自身が両者の架け橋となっていただくことです。内科での血糖値の検査結果(HbA1cなど)を歯科で共有し、歯科での治療状況を内科の先生に伝える。
このように情報を繋いでいただくことで、チーム全体があなたの体の状態を正確に把握し、より安全で効果的な治療計画を立てることができます。医師と患者様が二人三脚で取り組むことで、お口と全身のトータルな健康管理が実現し、病気の進行を「予防」することに繋がります。
まとめ|専門家に相談することが、最初の一歩

不安を抱えたままにしないための行動指針
この記事を通じて、歯周病と糖尿病の複雑な関係をご理解いただけたかと思います。それと同時に、「自分はどうなのだろう」という新たな不安を感じられたかもしれません。その不安を抱えたままにせず、具体的な行動に移すことが何よりも大切です。
まず、かかりつけの内科医に、ご自身の血糖コントロールの状態(HbA1cなど)を確認し、「歯科治療を受けたい」という意思を伝えてください。次に、ご自身の服用薬を正確に伝えるため、「お薬手帳」を準備しましょう。
そして、糖尿病への理解がある歯科医院へ、「検診と相談」を目的として予約を取ってください。ご自身の状態を専門家の視点から客観的に把握することが、漠然とした不安を解消し、適切な次の一歩を踏み出すための重要な確実な方法です。
歯周病治療がもたらす全身の健康への恩恵
歯周病の治療は、お口の中だけの問題ではありません。歯ぐきの慢性的な「炎症」をコントロールすることは、血糖値を下げるインスリンの働きを助け、糖尿病の管理に良い影響を与える可能性があります。
これは、歯周病と糖尿病の「負の連鎖」を断ち切るための重要なアプローチです。さらに、お口の炎症を抑えることは、血流に乗って全身に広がる炎症性物質を減少させ、動脈硬化を抑制し、心筋梗塞や脳梗塞といった他の「全身疾患」のリスクを低減させることにも繋がります。
つまり、歯科医院で行う歯周病の「予防」と治療は、歯を守るだけでなく、あなたの将来の健康を守るための、将来的な健康リスクの低減に役立つ取り組みといえます。
「まずは相談」から始まる、より良い未来への道
糖尿病という持病と向き合いながら、歯科医院の扉をたたくことには、少し勇気が必要かもしれません。
しかし、特別な準備や覚悟は不要です。「最近、歯ぐきの状態が気になる」「自分の口の中がどうなっているか知りたい」といった、些細なきっかけで十分です。私たち歯科医療の専門家は、一方的に治療を進めるのではなく、まずあなたの声に耳を傾け、不安や疑問を共有することから始めます。現状を正確に把握し、あなたに合った治療やケアの選択肢を一緒に考えるパートナーです。
その「相談」という一歩が、不安を安心に変え、内科医とも連携した、より良い健康管理への道を拓きます。どうぞ、一人で悩まず、私たち専門家を頼ってください。
監修:青山一丁目 麻布歯科
所在地〒:東京都港区赤坂8-5-32 田中駒ビル1F
電話番号☎:03-6434-9877
*監修者
青山一丁目 麻布歯科
ドクター 安達 英一
*出身大学
日本大学歯学部
*経歴
・日本大学歯学部付属歯科病院 勤務
・東京都式根島歯科診療所 勤務
・長崎県澤本歯科医院 勤務
・医療法人社団東杏会丸ビル歯科 勤務
・愛育クリニック麻布歯科ユニット 開設
・愛育幼稚園 校医
・愛育養護学校 校医
・青山一丁目麻布歯科 開設
・区立西麻布保育園 園医
*所属
・日本歯科医師会
・東京都歯科医師会
・東京都港区麻布赤坂歯科医師会
・日本歯周病学会
・日本小児歯科学会
・日本歯科審美学会
・日本口腔インプラント学会
投稿日:2025年10月30日